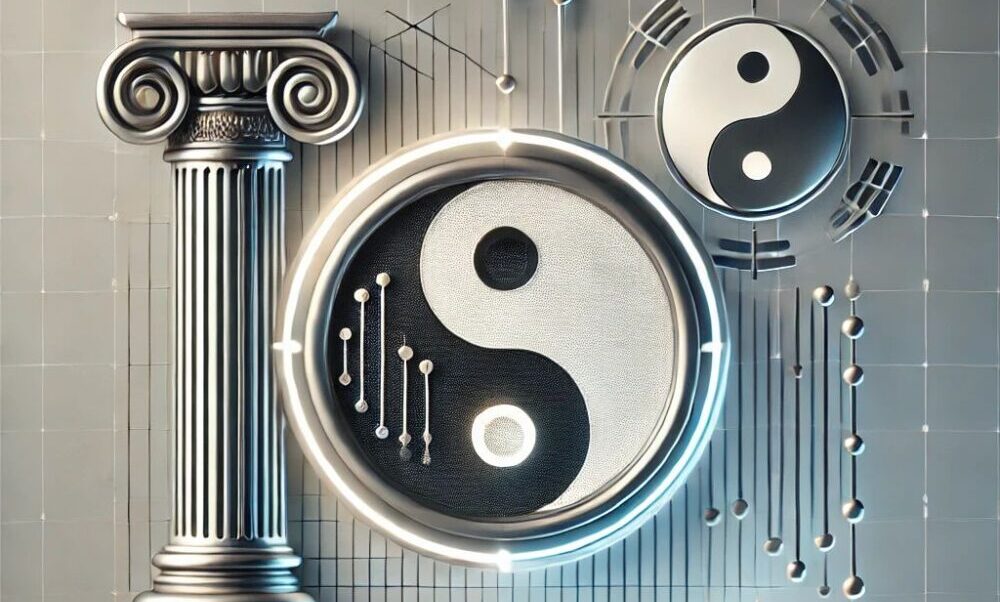介護サービスとは、介護保険制度に基づいて「要支援」または「要介護」の認定を受けた方が利用できるサービスの総称です。訪問介護・通所サービス・ショートステイをはじめ、施設サービスや地域密着型サービスなど、さまざまな形態があります。また、自治体独自の夜間対応型や巡回・随時対応型のサービスも提供されており、利用者の状況やニーズに応じた支援が可能です。
再認定(更新認定)について
介護認定には有効期間があり、認定の更新(再認定)によって再び認定が行われます。一般には12~36か月の有効期間が設定されますが、自治体によっては最長で48か月(4年)まで延長されるケースもあります。
また、心身の状況が変化した場合には「区分変更申請」によって更新期間を待たずに再認定を受けることも可能です。この場合は通常、6~12か月ほどの短期間の有効期間が設定されます。
「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の違い
- 介護保険被保険者証
介護保険の被保険者であることを証明する証です。65歳以上の第1号被保険者には自治体から自動的に交付されます。40~64歳の第2号被保険者は、特定疾病による要介護認定を受けた場合に交付されます。この証には要介護度も記載されており、有効期間は認定に応じて数年単位です。 - 介護保険負担割合証
利用者がその年度に支払う自己負担割合(1~3割)を示す証明書です。前年の所得や世帯状況に基づいて判定され、通常は毎年7月頃に発送され、8月1日~翌年7月31日までの1年間が有効期間です。
「要介護度」と「自己負担割合」の関係
「要介護度」は日常生活に必要な支援の度合いを表し、「要支援1〜2」や「要介護1〜5」、「非該当」の8段階に分類されます。この認定によって受けられるサービスの種類や支給限度額が決まります。
一方、自己負担割合は所得や世帯構成に応じて1~3割に設定され、介護サービスを利用した際の実際の支払い額に影響します。つまり、同じ介護度でも自己負担割合によって負担額は大きく変動します。
「要介護度」の見直しを依頼したい場合
- 区分変更申請
心身の状況が変化した場合、更新を待たずに再認定を求められる手続きです。主治医の意見書や調査に基づいて、通常6~12か月程度の有効期間で再認定されます。調査員には状況を正確に伝えるようにし、必要に応じて家族が同席したりメモを用意したりすることが有効です。 - 審査請求(不服申し立て)
認定結果に納得できない場合には、都道府県の介護保険審査会に正式に異議を申し立てることができます。ただし、結果が出るまでに数か月かかることがあります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 介護サービス | 要支援・要介護認定者が受けられる居宅・施設・地域密着型サービスなど |
| 再認定 | 更新認定(数年有効)と、状況変化時の区分変更申請(6〜12か月有効)の二つの仕組み |
| 被保険者証 vs 負担割合証 | 被保険者証:本人の認定・保険加入の証明 負担割合証:自己負担率を示し年度ごとに発行される |
| 要介護度と負担割合 | 要介護度でサービス内容が決まり、負担割合によって支払い額が変動 |
| 見直し手段 | 状況変化 → 区分変更申請 結果に不満 → 審査請求 |
※介護サービス全般については、以下が非常に参考になりました。
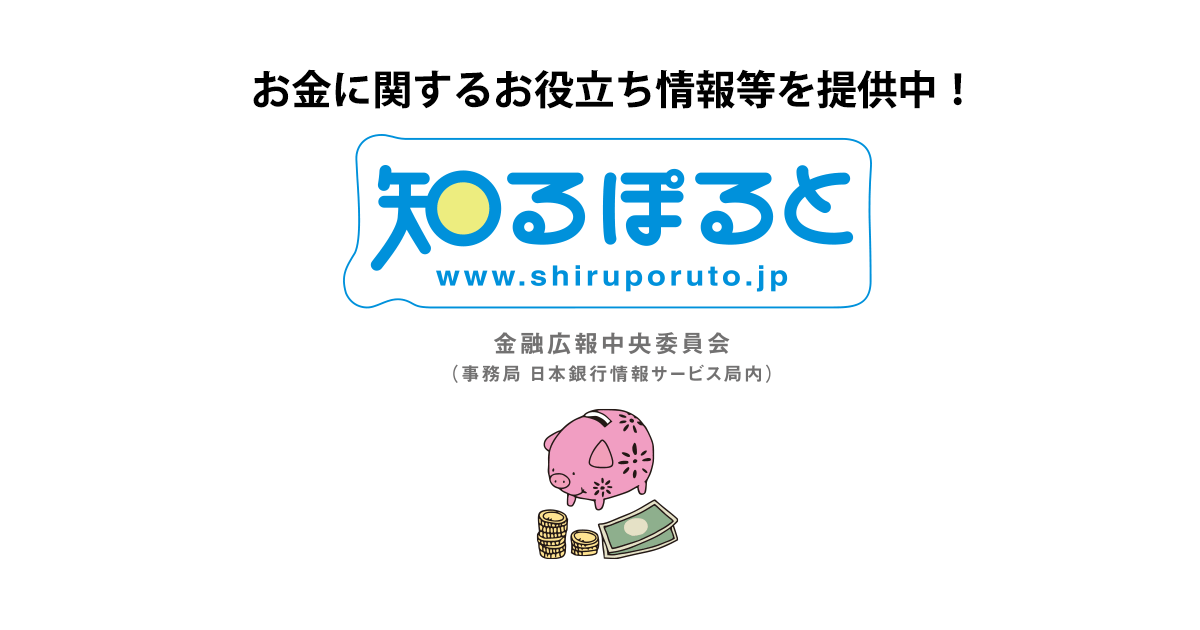
介護サービスの利用 ─ 介護にまつわる基礎知識 ~介護保険、成年後見、福祉サービス~|知るぽると
「介護にまつわる基礎知識」では、「介護保険」、「成年後見制度」、「福祉サービス支援事業」の仕組みなどについて、わかりやすく解説しています。