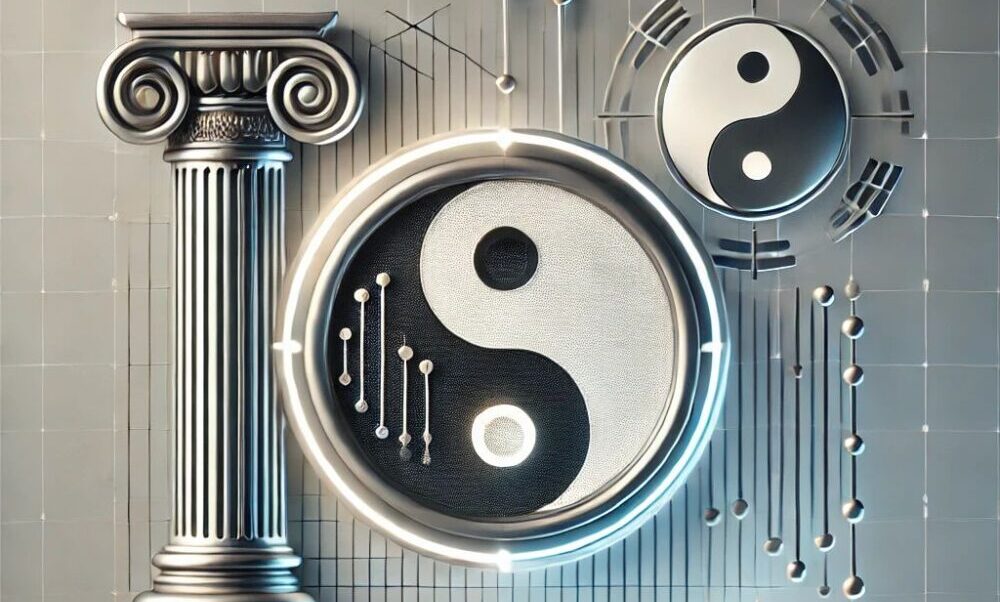先日、高齢の父に補聴器が必要になったため、初めて補聴器サロンに同行しました。その際、自分が「補聴器」に関する正確な情報をまったく把握できていないことを痛感しました。
そこで、いろいろ調べてみましたので、備忘録として以下に示します。
補聴器と集音器の違い
自分は全く認識がなかったのですが、この二つは本質的に異なる製品だそうです。
- 医療機器か一般機器かの違い: 補聴器は厚生労働省によって認証された管理医療機器であり、品質・安全性・有効性に関する厳しい基準をクリアした医療用製品です。一方、集音器は オーディオ機器(家電製品) に分類され、医療機器としての認証を受けていません。そのため補聴器は販売にも許可が必要ですが、集音器は家電扱いのため誰でも容易に販売・購入できます。
- 音の調整機能の違い: 補聴器はユーザーそれぞれの聴力に合わせて周波数ごとに細かく音を調整(フィッティング)できます。高音域が聞こえにくければ高音を、低音が聞こえにくければ低音を、と専門家が個別に調整してくれるため、一人ひとりに合った最適な補正が可能です。これには認定補聴器技能者など専門知識を持つプロのサポートが欠かせません。
一方、集音器は製品にもよりますが周波数ごとの細かな調整機能がなく、全ての音を一律に増幅するものが一般的です。そのため周囲の雑音までまとめて大きくなり、かえって肝心な会話が聞き取りにくいケースもあるようです。 - 価格帯や税区分の違い: 一般に補聴器は高価で、集音器は安価といわれます。この違いは上記の医療機器かどうかに起因します。補聴器は一台ごとに医療機器認証番号が付与され、製造から販売まで厳格に管理されているためコストがかかりますが、集音器はそうした管理が不要なため流通コストが低く価格も割安に見えます。また補聴器は「一定の身体障害者用物品」として消費税非課税ですが、集音器は課税対象です。購入時に消費税がかかるかどうかで、補聴器か集音器かを見分けることもできます。
- 公的補助の対象か否か: 補聴器が医療機器であるのに対し、集音器は単なる音響機器であるため、公的な補助制度の対象となるのは補聴器のみです。
補聴器の種類と選び方のポイント
補聴器にはさまざまな形状・タイプがあり、特徴や適している聴力の程度が異なります。選定には、聴力の程度や生活スタイル、使い勝手などを総合的に考慮することが大切とのことです。
- 耳かけ型補聴器(BTE/RIC): 本体を耳の後ろ側にかけ、チューブや細いコードを通じて音を耳に届けるオーソドックスなタイプです。操作が比較的簡単で電池も大きめのため電池寿命が長く、初めての方にも扱いやすい傾向があります。軽度から高度難聴まで幅広い聴力に対応でき、音のこもりも少ないため装用時の違和感も少なめです。本体が耳の後ろにあるため一見して補聴器と分かりやすい欠点はありますが、最近はカラフルでおしゃれなデザインも増えています。高齢者の場合、付け外しのしやすさや頑丈さという点でも耳かけ型は優れ、豊島区や新宿区の補聴器支給事業でも耳かけ型が推奨・提供されています。
- 耳あな型補聴器(ITE/CIC): 耳の穴の中に収まるオーダーメイドタイプの補聴器です。外見上目立ちにくくマスクや眼鏡の邪魔にならない利点があり、補聴器を付けることへの心理的ハードルを下げてくれます。一方で本体が小型な分電池も小さく操作が難しい場合があります。また耳穴の形状によっては作れないこともあり、高度難聴には対応しづらい(軽度~中等度難聴向け)という制約があります。紛失すると見つけにくい点にも注意が必要です。指先が不自由な高齢者には電池交換など取り扱いが負担になる場合もあるため、見た目の目立たなさと取り扱いの簡便さを天秤にかけて判断すると良いでしょう。
- ポケット型補聴器: ポケットサイズの本体とイヤホンがコードで繋がった昔ながらのタイプです。本体をポケットや首から下げて使用し、手元でスイッチやボリューム操作ができるため操作性が非常に良いのが魅力です。価格も比較的安価(数万円台)で導入しやすい傾向があります。一方でコードが邪魔になることや、身体からコードが伸びるため装用が目立ちやすいデメリットもあります。中等度~高度難聴に対応する製品が多く、手先の器用さに不安がある方には有力な選択肢です。
- メガネ型補聴器: 眼鏡のツル(フレーム)部分に補聴器の機能を組み込んだタイプです。見た目は普通の眼鏡と変わらないため周囲に補聴器と気付かれにくく、視力矯正も同時にできます。ただし常に眼鏡をかける習慣がない方には不向きで、対応する補聴器も限られます。現在ではあまり主流ではありませんが、眼鏡が手放せない方には一石二鳥の選択肢となり得ます。
- 骨伝導型補聴器: 振動により骨を介して内耳に音を伝える特殊な補聴器です。外耳や中耳に問題があり通常の補聴器が使えないケース(伝音性難聴など)で検討されます。装用にはヘッドバンドや眼鏡型フレームを用いることが多く、機器価格も片耳15~20万円以上と高額になります。取り扱っている医療機関・業者も限られるため、一般的なケースではまず通常の空気伝導補聴器を試し、どうしても適合しない場合に専門医と相談の上で検討しましょう。
選択のポイント: 補聴器を選ぶ際は、まず耳鼻科で聴力の程度や難聴のタイプを確認し、その上で補聴器の専門店で相談することが大切です。上記の各タイプのメリット・デメリットを踏まえ、実際に使用する人の聞こえの状態や要望(目立たない方が良い、操作は簡単が良い等)、予算をバランスよく考慮しましょう。認定補聴器技能者のいる専門店であれば、適切な機種選びから調整まで親身にサポートしてくれます。まずは気軽に相談し、実際に試聴・試着してみることをおすすめします。
初めて補聴器を使い始める場合の注意点
高齢者が初めて補聴器を装用する際には、最初から完璧に使いこなそうとせず徐々に慣れていくことが重要だそうです。補聴器を付け始めた当初は、「今まで聞こえていなかった生活音が急に耳に入ってくる」ため音が大きく騒がしく感じられるようです。
- 静かな環境から慣らす: 補聴器の音に慣れるには、まず静かな室内で時計の秒針の音など単調な音を聞く練習から始めると良いとされています。自分の声に慣れるため、本を声に出して読む練習も効果的です。いきなり人混みや騒がしい場所で使うより、家庭内など静かな環境で短時間から試しましょう。
- 徐々に装用時間を延ばす: 最初から長時間連続で使うとストレスや疲労の原因になります。最初は30分~1時間程度から始め、疲れたら無理せず外して休憩してください。「早く慣れよう」と無理に長時間つけっぱなしにする必要はありません。毎日少しずつ使う時間を増やし、数週間~1か月かけて日常的に装用できるようにしていきます。
- 騒音下での聞こえに戸惑わない: 補聴器に慣れていないうちは、街の雑踏やテレビの音など雑音ばかりが耳についてしまうことがあります。しかし使い続けていくと脳が必要な音と不必要な音を徐々に選別できるようになり、騒がしい中でも会話に集中しやすくなります。最初は戸惑うかもしれませんが、「脳のトレーニング中」と考えて根気強く付き合ってみましょう。
- 家族も協力を: 家族は補聴器装用者に向かってはっきり顔を見て話す、ゆっくりめに話すなどコミュニケーションの工夫をしてください。補聴器を付けたからといって完璧に若い頃の聴力が戻るわけではありません。周囲のサポートも併せて、使用者がポジティブな印象を持てるよう励ましましょう。
- 定期的な調整: 使い始めの数か月は、とくにこまめに販売店で音の調整をしてもらうことも大切です。「会話は聞こえるようになったがテレビ音声が聞き取りにくい」等の要望があれば遠慮なく伝え、適切なプログラム設定に調整してもらいましょう。購入直後は月に数回、その後も少なくとも年に一度は専門店で点検・調整を受けるくらいの気持ちでいると安心です。
補聴器の試用から購入までの流れ
補聴器は想像してよりもはるかに高額でした。ですので、いきなり購入するのではなく、耳鼻科の先生や(相談できる場合は)ケアマネさんに相談するのがよいかと思います。
自分の父の場合、事前に耳鼻科で診てもらったことで聴力検査をしっかり実施してもらうことができましたし、耳垢除去処理なども事前にやってもらえました。
また、ケアマネさんからは区の助成金制度についての情報をもらうことができ、事前に申請をしたおかげで購入条件などもクリアにした状態で専門店に行くことができました。
- 耳鼻咽喉科での診察・相談: 聞こえが悪いと感じたら、まずは耳鼻科で診察を受けましょう。耳垢詰まりや中耳炎など治療可能な原因がないか確認し、難聴の程度やタイプを検査してもらいます。
- 補聴器専門店で相談・試聴: 聴力データや医師の意見書を持って、認定補聴器専門店に行きましょう。店では難聴の状況や生活環境、予算などのヒアリングを経て数種類の補聴器を提案してくれます。その場で実際に耳につけて音の聞こえ方を試す(試聴)ことができます。多くの店舗は無料の試聴サービスや貸出機を用意しており、自宅で数日~数週間試用することも可能です。この試用期間に家族との会話やテレビ視聴など日常環境で効果を確かめましょう。
- 機種の決定とフィッティング: 試用の結果を踏まえて、購入する機種・タイプを決定します。購入前に細かな音のフィッティング(調整)を行い、使う人の聴力や好みに合った音質・音量に設定してもらいます。耳あな型の場合は耳型の採型(耳型の型取り)をしてオーダーメイド製作となるため、完成までに数日~数週間かかります。その間、仮の補聴器を貸してもらえる場合もあります。
- 補聴器の購入・受け取り: フィッティングが完了し購入を決めたら、正式に購入手続きを行います。補聴器は原則非課税の商品なので消費税はかかりません。購入時に保証内容(故障修理保証や紛失保証の有無)も確認しましょう。
- 購入後のフォロー: 補聴器は買って終わりではなく、始まりです。購入後1~3か月は特に頻繁に店で微調整や使い方トレーニングを受けながら、自分に最適な状態に仕上げていきます。以降も定期点検やクリーニング、必要に応じ聴力再測定と設定変更など、長く付き合っていくものと心得ましょう。自宅から通いやすい店舗を選ぶことも大切なポイントです。
※補足:公的補助を利用する場合、購入前に必ず区役所等へ申請し、承認(決定通知)を受けてから購入する流れになります。補助制度の詳細については次章「その他:補助金・紛失防止など」で述べます。申請前に購入してしまうと補助対象外になりますので注意してください。
補聴器の継続的なメンテナンスについて
補聴器を良好な状態で長持ちさせるには、日々の手入れと定期的なメンテナンスが欠かせないとのこと。精密機器である補聴器は、耳あか・汗・湿気などによって故障や劣化が生じやすいそうです。
- 毎日の簡単なお手入れ: 補聴器のマイク部分(音の入り口)やスピーカー部分(音の出口)に耳あかやホコリが詰まると音がこもったり出なくなったりします。柔らかい布や専用ブラシで表面の汚れを拭き取り、付属の耳せん(イヤーモールド)は取り外せる場合、水洗いして十分乾燥させてから装着し直します。特に耳あな型は耳垢が内部に溜まりやすいので、こまめな掃除が必要です。
- 湿気対策(乾燥保管): 補聴器は水や湿気に弱いので、使い終わったらそのまま放置せず乾燥ケースに保管しましょう。市販の乾燥ケースや乾燥剤を利用して、一晩かけて汗や湿気を飛ばす習慣をつけます。ただし空気電池(補聴器用電池)は極端な乾燥が苦手なため、乾燥ケースに入れる際は電池を外すか電池蓋を開けておきます。入浴時や洗顔時はもちろん、雨の日もできるだけ濡らさないよう注意し、誤って濡れた場合は速やかに電池を抜いて乾燥させましょう。
- 電池・充電の管理: 空気電池式の補聴器なら電池は1週間程度で切れるため、常に予備を持ち歩き早めに交換します。夜は電池蓋を開けて電源を切りつつ通気させると良いでしょう。充電式の場合も毎晩決まった時間に充電器にセットし、電源が確実に切れるようにします。長期間使わないときは電池を抜いて保管してください。
- 耳や装用状態のチェック: 耳掃除は行き過ぎると外耳炎の原因になりますが、耳垢が多い方は耳鼻科で適宜クリーニングしてもらうと補聴器の効果が安定します。装用中、耳に痛みやかゆみを感じたら無理に使い続けず専門家に相談しましょう。耳型が変化してフィットが悪くなることもあるため、異常を感じたら早めに点検に出すことが肝心です。
- 定期点検・調整: どんなに丁寧に使っていても、汚れや経年劣化は避けられません。少なくとも年に1回は購入店で点検・クリーニングと調整を受けることをおすすめします。プロによる超音波洗浄や内部点検で故障を未然に防げますし、聴力変化に応じた再フィッティングで常に最適な状態を維持できます。また保証期間中であれば無償修理対応してくれる場合もあります。
その他:補助金・紛失防止などの注意点(豊島区・新宿区の場合)
最後に、補聴器に関連する公的補助制度や紛失防止策など、見落としがちなポイントについて整理します。ここでは、東京都豊島区・新宿区の制度を具体例にしています。
- 自治体による補聴器購入補助(金銭的助成): 東京都内では多くの自治体が高齢者向けに補聴器購入費の一部助成制度を設けています。
豊島区の場合:「高齢者補聴器購入費助成」という制度があり、満65歳以上で中等度難聴と診断された区民を対象に補聴器代の一部を助成しています。身体障害者手帳(聴覚障害)を持っていない中程度難聴の高齢者が対象で、所得区分により上限5万円(非課税世帯)または2万円(課税世帯)が1人1回限り支給されます。申請には事前に地域包括支援センターへの相談と耳鼻科医の診断書が必要で、購入前に申請・承認を受けることが必須です。承認後に認定補聴器専門店で試聴・購入し、領収書を提出して助成金の振り込みを受ける流れです。なお助成は原則1人1台限りで、故障や紛失による再助成はありません。
新宿区の場合:「補聴器の支給等」として少し独特な制度になっています。満70歳以上で聴覚障害者手帳を持たない高齢者が対象で、以下の2つの方式から選択できます。
ひとつは区が指定する業者で補聴器(耳かけ型またはポケット型・片耳)を現物支給してもらう方式で、その際利用者負担額は2,000円(生活保護世帯等は負担なし)です。
もうひとつは自分で好きな補聴器を購入し、その費用の一部(上限33,000円、生活保護世帯等は35,000円)の助成を受ける方式です。
いずれも事前に区の高齢者支援課等で申請が必要で、耳鼻科医の聴力検査結果に基づき承認されます。新宿区では前回の支給から5年間は再申請不可となっており、紛失・故障の場合でも5年間は原則再支給されない点に注意が必要です。 - 補聴器の紛失防止策: 高齢者の場合、補聴器をどこかに置き忘れたり落として紛失してしまう不安もあります。紛失を防ぐために、メガネホルダーのようなストラップを補聴器本体に取り付けて衣服に留めておく方法があります。実際、子供用補聴器では落下防止バンドがよく使われますが、高齢者でも外出時に不安があれば活用するとよいでしょう。また就寝時や入浴時に外した補聴器は決まったケースに入れる習慣をつけ、家族にも補聴器の所在を気にかけてもらうようにします。補聴器メーカーによってはスマートフォンと連携して補聴器の位置検索や警告音発信ができる機種もありますので、紛失が心配な場合は販売店に相談してみましょう。
- 紛失・故障時の保証: 補聴器は高額なため、万一紛失した場合の保証も気になります。メーカーや販売店によっては、購入後1〜2年以内の紛失であれば1回限り無償または割引価格で再提供するといった紛失補償制度を用意している場合があります。購入時には保証内容についてしっかり確認し、必要に応じて延長保証や保険に加入すると安心です。ただし公的補助で手に入れた補聴器については上述の通り再助成が受けられないため、一層自己管理に気を付けましょう。
参考資料・情報源: 豊島区公式サイト、新宿区公式サイト、補聴器メーカー・専門店の解説ページ等.