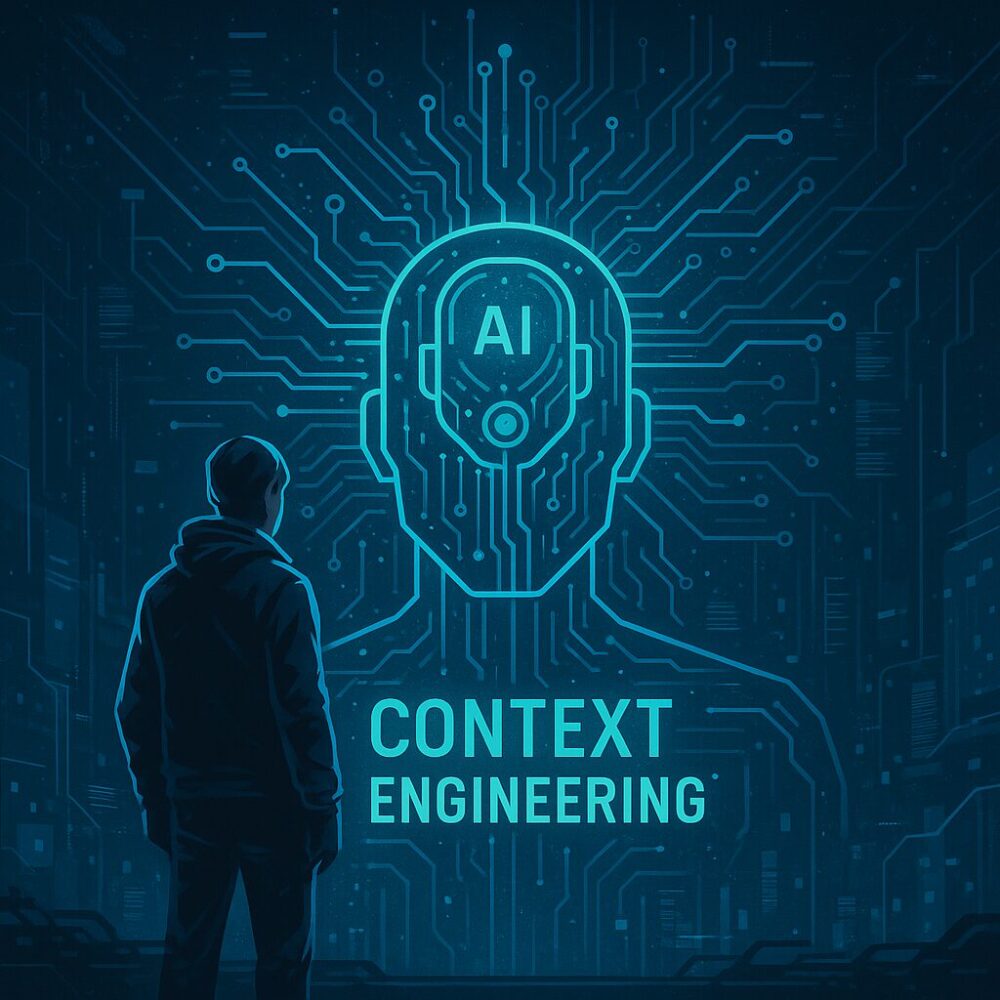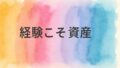はじめに
最近、仕事以外でも生成AIを使う場面がぐっと増えてきました。文章作成やアイデア出し、さらにはちょっとした調べものまで、まさにAIは頼れるパートナーになりつつあると感じています。
生成AI活用でよく語られるのが「プロンプト・エンジニアリング」─効果的な指示文(プロンプト)の書き方を工夫する技術-ですが、自分としては「どのような情報を共有するか」も外せず重要だと感じます。そのように、AIにタスクを正しくこなしてもらうために、必要な情報をどのように準備・整理し、どんな形で提示するかを設計する考え方である「コンテキスト・エンジニアリング」について、まとめてみます。
生成AIを使いこなすためのポイント
ChatGPTなどの生成AIは、質問に答えたり文章を作成したりと、多彩に活用できます。ですが、実際に触れてみると「同じ質問でも回答の質にばらつきがある」「思った通りの文章が出ない」と感じた方も多いのではないでしょうか。
生成AIをうまく使いこなすためのポイントは大きく二つあります。
- 適切な指示(プロンプト)を与えること
- 必要な知識や文脈(コンテキスト)を整理して渡すこと
これまで特に注目されてきたのは前者「プロンプト・エンジニアリング」ですが、実際には後者も同じくらい重要です。むしろ近年では「プロンプトを含む情報環境全体を設計する」=コンテキスト・エンジニアリングという考え方が鍵を握るようになってきています。
「コンテキスト・エンジニアリング」とは
「コンテキスト・エンジニアリング」とは、AI(特に大規模言語モデル: LLM)がタスクを正確に解決できるよう、必要なすべての文脈情報をAIに提供・設計する技術です。ここでいう「コンテキスト」とは、単にAIへの指示文だけでなく、AIが回答を生成する前に参照できるあらゆる情報を指します。
具体的には次のような要素が含まれます。
- システム指示:AIの役割や口調、ルールを定める(例:「あなたはプロの校正者です」)。
- ユーザープロンプト:ユーザーからの具体的な依頼や質問。
- 状態・履歴(短期メモリ):直近の会話の流れを保持し、一貫性を担保。
- 長期メモリ:ユーザーの嗜好や知識などを長期的に蓄積。
- 検索された情報(RAG):AIが内部に持たない最新情報や文書を外部から検索して組み込む。
- 利用可能なツール:AIが操作できる外部機能やAPI(在庫管理やカレンダー登録など)。
- 構造化された出力指定:回答を箇条書きやJSON形式にするなど、使いやすい形で出力させる。
このように、コンテキストは情報環境全体です。プロンプトはその一部にすぎません。
「プロンプト・エンジニアリング」との比較
「プロンプト・エンジニアリング」は、与える指示文を工夫することに重点を置きます。例えば「3つの箇条書きで説明して」「初心者にもわかるように」といった指示を最適化するのがこれに当たります。
一方「コンテキスト・エンジニアリング」は、プロンプトを含むAIが参照する情報全体を設計する広い概念です。システム指示や履歴、外部知識、出力フォーマットまで組み合わせ、タスクに最適な環境を整えることを指します。この概念は多くのAI専門家からも支持されていて、優れたAI活用の秘訣は“魔法のプロンプト”探しではなく、質の高いコンテキストを設計することなのです。
「コンテキスト・エンジニアリング」のためのデータ前処理
コンテキストの設計で特に重要なのがデータ前処理です。AIが一度に処理できる情報量(コンテキストウィンドウ)には限界があり、また不要な情報が混じるとAIは本質を見失い、誤解した回答を返すことがあります。
そこで必要なのが、情報を取捨選択・要約・整形する工程です。
- 要約:長い文章をコンパクトに整理する
- 抽出:関連部分だけを取り出す(RAGでよく用いられる手法)
- 構造化:表形式や箇条書きに変換して理解しやすくする
- 正規化:日付や数値の表記を統一する
- マスキング:機密情報や不要な要素を除去する
例えば「先週の会議の議事録を要約して」と依頼しても、AIには「先週=何日?」「どの会議?」といった前提知識はありません。こうした“欠けている情報”を補ってあげることが、まさにコンテキスト・エンジニアリングの役割です。
また、長い履歴や全文検索の結果を丸ごと与えるのではなく、「要約」や「断捨離」でスリム化し、限られたコンテキスト枠に最大限の有益情報を詰め込むことが高品質な文章生成につながります。
「コンテキスト・エンジニアリング」の実践ポイント
とりあえず、取り組みやすい具体的な実践方法を整理すると以下の通りです。
- 情報を前処理する習慣をつける:要約してから渡す/必要部分だけ抜き出す
- 出力形式を必ず指定する:箇条書きや表形式にすれば再利用が容易
- 小さく試して改善する:いきなり完璧を目指さず、AIの出力を見て前処理や指示を調整する
- セキュリティに配慮する:機微情報は必ずマスキングしてから入力する
- 継続的に更新する:外部データやルールは環境の変化に応じて見直す
まとめ
生成AIを「思い通りに使いこなす」ためには、単なる指示文の工夫(プロンプト・エンジニアリング)にとどまらず、AIに渡す情報環境そのものを設計する視点が欠かせません。その中心にあるのが「コンテキスト・エンジニアリング」です。
情報を前処理し、必要な知識やルールを整理して与えることで、生成AIは一段と信頼できるパートナーになります。今後は「魔法のプロンプト」ではなく、「賢いコンテキスト設計」こそが、AIを活かす最大の鍵になると思われます。